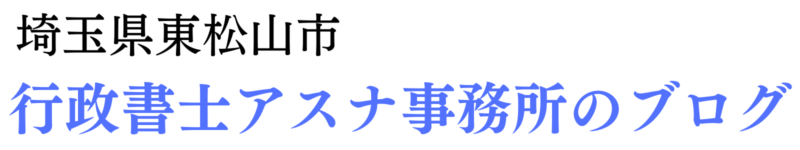行政書士 田村
行政書士 田村先日、次のようなお問い合わせをいただきました。



先生!
なんか適正化事業実施機関というところから、
営業所に討ち入りに来るとの手紙が!
ど、どうしましょう💦



社長、落ち着いてください!
ただの「巡回指導」ですから大丈夫ですよ。



でも、何を用意すればいいのかもわかりません!



届け出書類とか、法定日常帳票類などですね。
普段の業務で使っている書類があれば大丈夫ですよ。



そ、そうですか。
初めてのことなので、慌ててしまいました💦
ところで巡回指導って監査とは違うのですか?



詳しくは説明しませんが、「監査」は陸運支局が処分前提で行うのに対して、
「巡回指導」は適正化事業実施機関が、法令を守っているかをチェックし、守れていない場合に指導するものです。
最初はちょっと緊張しますが、最後は和やかな雰囲気で終わることが多いですよ。
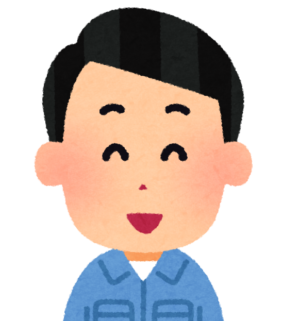
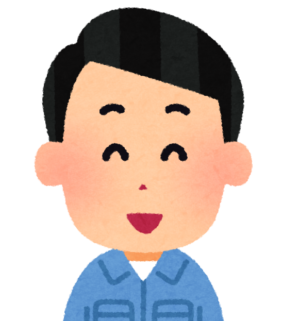
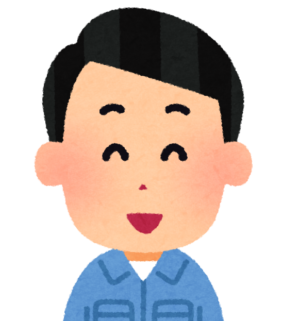
それを聞いて安心しました!



社長、安心しているところもうしわけないのですが、
巡回指導は監査のきっかけになることもあるんですよ。
通知に同封されていた、書類に目を通しておいてくださいね!
茶番はここまで!
埼玉県のほぼ中心、東松山市で行政書士をしている田村栄嗣です。
主要業務は運送業許可と10年の物流経験を活かした物流コンサルティングです。
他業種から親の経営する運送会社に入った2代目、3代目社長様にはある共通の特徴が多くみられるます。
その特徴は以下のとおりです。
・役員法令試験を受けていないので物流に関する法律に疎い
・会社の現状を把握できていない
これらの特徴が顕在化するのが、2代目、3代目社長様にとって初めての「巡回指導」のときなのです。
この記事では、そんな社長様の「巡回指導のポイントと対策がわからない」といった疑問にお答えするものです。
この記事を読めば以下のことがわかります。
・巡回指導とは何か
・巡回指導の38項目と重点項目の評価方法
・巡回指導の38項目と重点項目の市道を乗り切るポイントと対策
巡回指導


巡回指導とは
巡回指導とは、適正化事業実施機関が運送事業者に対して行ないます。
適正化事業実施機関とは、平たく言ってしまうと、地方運輸局に指定された「各都道府県トラック協会」のことです。
巡回指導では指導員(たいてい二人組)が、運送事業者の営業所を訪ね、帳票類をチェックしながら事業者にヒアリングを行います。
その際に、法令違反、特に輸送の安全に関する法令に違反がみられる場合に、改善指導を行います。
地方適正化事業実施機関は行政機関ではありませんが、行政機関に準ずる権限を持っています。
行政処分は出来ませんが、違反を地方運輸局に報告し、それが監査のきっかけになることもあります。
巡回指導の目的
上に書いたように巡回指導の目的は、行政処分ではなくあくまでも法令違反をした運送事業者に違反の改善指導をすることです。
巡回指導の周期
通常、2年に1回ということになっていますが、埼玉県では人手不足のためか3~5年に1回程度の割合になっています。
先日、巡回指導を終えた事業者様は前回の巡回指導が平成29年だったというので、6年ぶりということになります。
コロナ禍で見合わせていたところもあるようで、これから多くの事業者が巡回指導を受けそうです。
いつ通知が来るの?
通常、巡回指導実施日の約1ヵ月前に、地方適正化事業実施機関から運送事業者に書面で通知がいきます。
2代目、3代目の社長さんで初めてこの通知を受け取ると必要以上に慌ててしまう方もいらっしゃいますが、監査と違ってあくまでも指導ですので落ち着いて対処してください。
書類は封筒に入っており、封筒の中身は、以下のとおりです。
・巡回指導実施の日時などを記した通知
・運送事業者が用意すべき書類一覧
・自主点検表
・アンケート用紙
巡回指導の38項目と重点項目の評価基準


巡回指導の指導項目は38項目で評価は5段階
38の各項目が「適」「否」で評価されます。
総合評価はA~Eの5段階で、評価され「適」判定の割合で決定します。
①90%以上 ⇒A 適35以上 否3以下
②80%~90%未満 ⇒B 適31以上 否7以下
③70%~80%未満 ⇒C 適27以上 否11以下
④60%~70%未満 ⇒D 適23以上 否15以上
⑤60%未満 ⇒E 適22以下 否16以上
重点項目が一つでも「否」の場合、総合評価が1段階引き下げられます。
二つ以上「否」があった場合も、引き下げは1段階です。
指導項目は、大項目が7つあり、小項目が38あります。
大項目は以下のとおりです。
・事業計画(8項目)
・帳票類の整備、報告(5項目)
・運行管理など(13項目)
・車両管理など(5項目)
・労基法など(4項目)
・法定福利費(2項目)
・運輸安全マネジメント(1項目)
38項目の中で特に重点項目とされているものは以下の9項目です。
これら9個の重点項目に1つでも違反していると、総合評価が1段階下がります。
ただし、重点項目違反が複数あっても下がるのは1段階のみです。
ちなみに重点項目は、運行の安全や運転者の労務管理に関することです。
・運行管理者が選任され、届出されているか
・過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか
・点呼の実施及びその記録、保存は適正か
・乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか
・特定の運転者に対して特別な指導を行っているか
・特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか
・整備管理者が選任され、届出されているか
・定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか
・労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)
巡回指導の評価が悪いとどんなデメリットがあるの?
評価がEだと監査の可能性もある
総合評価が「E」で、重点項目の中でも、運転者の健康に関する項目に法令違反があると、期限を定めて改善報告が求められます。
これらを無視すると、地方運輸局に報告が上がり監査となります。
評価が2回連続でDだとやはり監査の可能性
前回の巡回指導の総合評価が「D」だった事業者様は気を付けてください。
2回続けて「D」を取ると、やはり総合評価「E」の場合と同じく、監査の可能性があります。
悪質事業者は半年に1度監査が入ることに
令和5年4月1日から、「D・E」を取った事業者は半年後に2回目の巡回指導が行われることになりました。
2回目の巡回指導でも「D・E」だった事業者にはまた半年後に巡回指導が行われます。
この3回の巡回指導の総合評価がすべて「D・E」だった運送事業者は監査の対象となります。
ここを抑えよう!巡回指導を乗り切るポイントと対策
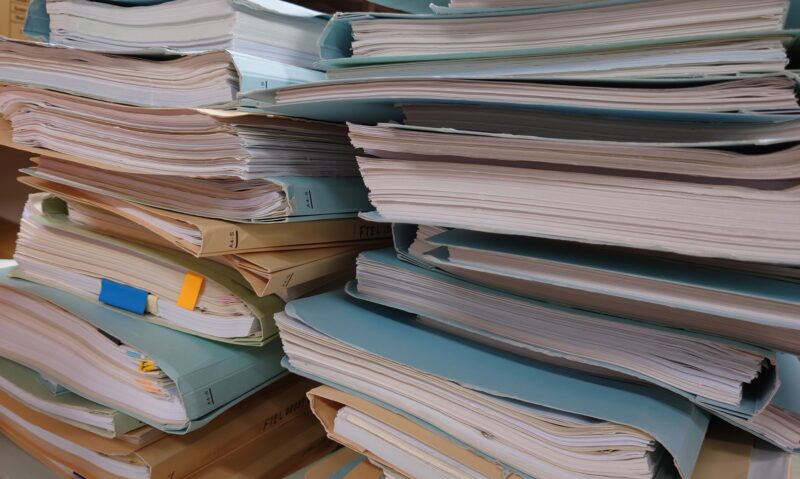
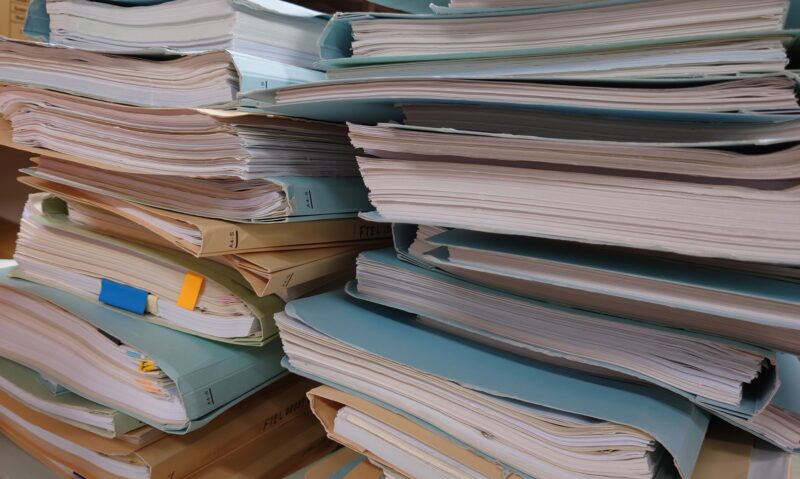
巡回指導というと、必要以上に身構えてしまう事業者様もいらっしゃいます。
しかし、健全な経営をしていれば、特に指導を受けることもなく総合評価も「A」がつくはずです。
むしろ、指導員に自社の欠点を指摘してもらい、以後の経営の健全化に役立てるくらいの気構えで受けて頂きたいところです。
24年問題がすぐそこまで迫っている現在、生き残るためにはやはり経営の健全化が必須です。
確かに、社長や役員だけの努力ではどうにもならない部分もありますが、これを機会に運転者と話し合いの場を設け、全社員一丸となって24年問題を乗り切って頂きたいと思います。
9つの重点項目は必ずクリアすること
9つの重点項目は全て、運行の安全と運転者の労働に関するものです。
国がいかにこれらを重く見ているか分かります。
運転者への定期の安全教育、特別教育はしっかり計画を立てて実施しましょう。
これらの教育は外部機関の力を借りるのも手です。
当事務所でも、安全教育の講師を承っております。
また、運転者の労務管理には、運転者自身の協力が不可欠です。
タコメーターの適切な切り替え、日報の作成は時間に追われる運転者さんは何かと忘れがち。
点呼係は運転者の疲れを労い、協力してもらいましょう。
社長や役員が安全教育の時に、指導することも効果的です。
2代目、3代目の社長さんは事業計画変更があったか確認すること
2代目、 3代目の社長様に多いのが、先代(中小零細事業者では殆どが親)からきちんと引き継ぎを受けていないことです。
会社の現状をきちんと把握できていない社長様は、思ったより多いと感じています。
実は、先代の社長様自身もきちんと把握できていない事も少なくありません。
先日、関わった事業者様のケースでは、営業所の建物を建て替えたため変更届を出さなければいけないところ、かなり長いことほったらかしていたということがありました。
会社の業態が少しでも変わる場合は、お知り合いの行政書士にお尋ねください。
変更認可届出書の控えがあれば、その足跡がたどれるのでなんとかリカバリできるのですが、控えが全くないと我々専門家でもお手上げということもありえます。
変更認可届出書の控えはとても大切なものです。
きちんと保管しておきましょう。
変更認可届出書の確認すると以下のことが分かります。
①本社
②営業所
③休憩施設
④車庫
⑤役員
⑥現在の車両の数
変更認可届けをしたかどうかわからない
変更認可届を出したかわからない場合は以下の手順を踏んでください。
①届出の控えを探す
②控えが見つかる⇒③へ
控えが見つからない⇒④へ
③現況と照らし合わせ相違が無い⇒OK
現況と異なる ⇒④へ
④運送業専門の行政書士に相談
帳票類はきちんとそろえること
帳票類でそろわないのが、運転日報と点呼記録簿です。
運転日報に関しては、運転者が面倒くさがって書いていない事業所が見受けられます。
点呼記録簿に関しては、そもそも点呼を行なっていない事業者があります。
運転日報の作成には運転者の協力が不可欠。
普段から運転者とコミュニケーションを取り、運転日報の重要性を教育指導しましょう。
点呼は、運転者のアルコール摂取状態や健康状態を確認する重要な業務です。
運行の安全は点呼から始まります。
そのことを忘れてはいけません。
また、帳票類がそろっていても、お互いに矛盾があることがあります。
特にタコメーターの記録と運転日報があっていないことが多いです。
これは、運転者がタコメーターの切り替えをきちんとしていないことから生じます。
その結果、指導員から、4時間以上の連続運転が行われていると指摘されることがよくあります。
運転者にタコメーターの切り替えをきちんと指導することも、社長や役員そして運行管理者の役務ですので、しっかり指導しましょう。
定期の安全講習と当別講習をきちんと行うこと
法定12項目の教育系を計画を立てて行う。
法定12項目とは、「事業者が乗務員に対して行う一般的な指導及び監督の指針(平成13年8月20日国土交通省告示1366号)」のことです。
1カ月に1項目ずつでなくてもかまいません。
例えば、3カ月に1回3項目ずつでもOKです。
巡回指導対策は運送業専門の行政書士へ





巡回指導に関して、ポイントをざっと見てきました。
取り合えず、取り組むべき方向性はつかめたのではないかと思います



先生の説明で、何とか一歩踏み出せそうです!



初めての巡回指導では、準備ができずに総合評価「D・E」を取ってしまう事業者さんも多くいらっしゃいます。
運送業専門の行政書士に対策を依頼するのがオススメです。
初めての巡回指導では、何をしたらよいかわからず、「D・E」を取ってしまう事業者さんをお見掛けします。
運送業専門の行政書士に対策をご依頼することをお勧めいたします。
先日の私が対策を承った事業者様は前回は総合評価「D」でしたが、今回は総合評価「B」となり監査にならずに済みました。
この事業者様は今回の巡回指導をきっかけに、事業の健全化に乗り出しました。
このように、ただ巡回指導を乗り切るのではなく、巡回指導をきっかけに自社の経営の見直しや事業の適正化を進めていっていただくのが私の願いです。
当事務所では、巡回指導・監査の対策指導を行っています。
巡回指導に不安を感じている事業者様、当事務所にお気軽のお問い合わせください!