埼玉のほぼ中心東松山市で行政書士をやっている田村栄嗣です。
本日は、「会社の印鑑」について詳しく解説していきます。
日本は世界でも珍しいはんこ社会です。何かにつけてポンポンとはんこを押しています。
もちろん会社も例外ではなく、むしろ会社のほうが日常的にはんこを押しています。
契約書にはんこ、訂正にはんこ、領収書にはんこなどなど。
それでは会社に必要なはんこについて解説していきます。
会社の印鑑は主に3つあって、一つは「実印」、もう一つは「角印」、そして最後は「銀行印」です。
法人設立のためにこの3つをセット販売するはんこ屋さんもあります。
それではそれぞれについてみていきましょう。
実印
人と同じように会社にも実印があります。会社と同じように役所に登録をしますが、会社の場合は市区町村役場ではなく本店所在地を管轄する法務局に登録します。
大抵は、会社の登記申請の時に登録をします。
会社の実印のことを「代表者印」とも言います。
私は会社を始めた頃、印鑑を押す欄にこの「代表者印」という字を見て、「代表者個人の実印」かと思ったことがあります。実は、会社の代表者の印鑑を代表者印として登録することもできるのですが、混乱の元ですので、会社の実印は別に作りましょう。
実印の形
実印には形式があって、「1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるもの」と決まっています。たいていは2重の円になっています。内円の中に「代表取締役印」、内円と外円の間に「会社名」が入っているのが一般的です。
会社の実印は個人の実印と同様に本人の確認のために用います。契約書など大事な書類に押す印鑑ですので、管理は厳重に行ってください。
一般的に会社の契約は個人の契約よりも金額が大きなことが多く、また、会社の実印の管理における過失は個人の場合より認められやすいので気を付けてください。
代表者印の例

私が以前経営していた会社の実印です。
会社の実印も個人の実印と同じように、法務局に印鑑登録をすると「印鑑カード」が発行されます。会社の印鑑証明が欲しい時に印鑑カードを忘れると、会社の実印を持っていても印鑑証明がとれないので気を付けましょう。ここは、個人の場合と一緒です。
私も、印鑑カードを忘れて事務所と往復した記憶があります。

印鑑証明取得までの流れとしては、
①管轄法務局に印鑑登録 ↓ ②印鑑カードの交付を法務局に申請 ↓ ③交付してもらった印鑑カードで印鑑証明を取得
となります。
設立後、すぐに契約書に印鑑を押す必要が出てくる場合もあるので、印鑑登録は早めに済ませましょう。
その他のはんこ
角印
角印は、会社の認印の役割を果たします。見積書や請求書・領収書に押したりします。日常業務ではこちらを使うことが多いです。大きさには特に決まりはありません。
ちなみに、行政書士の職員は角印です。この場合、大きさに決まりがあります。
会社の角印の例
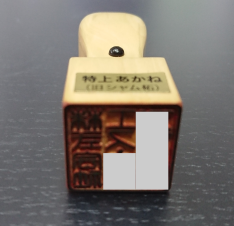
やはり私の会社の角印です。
銀行印
銀行口座を作るときに使う印鑑です。一般的に実印と同じ2重丸で内円の内側が「銀行之印」となっています。銀行印は、会社の実印で代用してもかまいません。私はハンコが多くなると管理が面倒なのでそうしていました。ただ、実印とは別に用意した方がセキュリティー上好ましいことは言うまでもありません。
銀行の預金の出し入れや振り込みなどだけではなく、手形・小切手の振出にも使います。
ゴム印
会社名、代表者名、会社の住所、電話番号、FAX番号、最近ではホームページのURLやメールアドレスなどが刻印されているはんこです。一体型のものもあるのですが、下のようにそれぞれがバラせるものがおすすめです。縦型もあります。このタイプでしたら、会社の移転や代表者、社名の変更もその部分だけ作り直せばいいので経済的です。
一つ持っていると大変重宝します。
まだ社名入り封筒を作るまでもない場合など、送り主のところにこれを押すだけです。
手間が省けるだけではなく、私のように字が汚い人はぜひ備えましょう。

本日はここまでです。お疲れさまでした。
会社設立に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください!
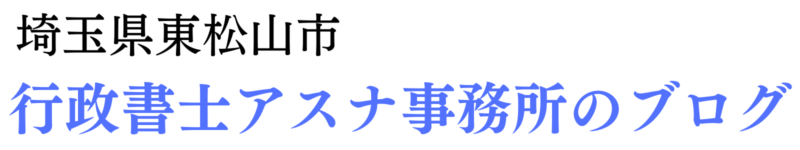


コメント